
【クロスの補修跡】2014年8月11日(月)お家の点検10年目(富山市Y邸)
2015/03/07
天井クロス同士の間を見ると、コークボンドの乾いた白く透明な補修跡が太陽光で反射していました。お客様が5年目点検後にDIYでクロスの隙間にコー…
詳細を見る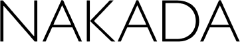

2015/03/07
天井クロス同士の間を見ると、コークボンドの乾いた白く透明な補修跡が太陽光で反射していました。お客様が5年目点検後にDIYでクロスの隙間にコー…
詳細を見る

2015/03/07
Q 冬の間はアルミサッシの結露が激しい。 [LDK/東側] [2階居室/南側] お客様は様々な結露対策を考えておられました。熱の伝導…
詳細を見る
2015/03/07
2014年8月6日(水)お家の点検10年目(富山市S邸) 所要時間 13:01~15:22 晴れ スタッフ 横窪、渡辺 【S邸の紹介】 色合…
詳細を見る
2015/03/07
[雨水枡] 雨水枡の点検を実施。特に異常ありません。 [建物前面/北西側] [汚水枡] 点検を実施。白い油脂等が少し溜まっていました。 …
詳細を見る
2015/03/07
屋根点検を実施。 屋根材は洋瓦仕様となっています。 瓦とスクリュー釘の間のゴムパッキンが劣化している状態。これらの現象をデジカメで撮…
詳細を見る
2015/03/07
玄関ドアの開く幅(開く軌道)以上の長さのポーチ屋根が直射日光(紫外線等)を遮っています。「木製玄関ドア」の対候性を維持するには「定期的な防水…
詳細を見る
2015/03/07
Q 塗装が剥がれてきた。 A 現状を確認。お客様との協議の結果、今回の塗装の範囲は「正面部分と側面はジョイント部分まで」となり、後日、見積書…
詳細を見る
2015/03/07
Q 折れ戸の開閉がしにくくなってきた。 A 現状を確認。この扉は上側にはレールがありますが、下側にはレールが無い仕様となっています。 [1階…
詳細を見る
2015/03/07
5年目点検では「うっすらと結露するが、いつもタオルで拭いている」とのことでお客様ご自身による拭き掃除が習慣化しているご様子でした。木製サッシ…
詳細を見る