天井取り付け型の換気システムです。1階、2階ともにONの状態。
Q お掃除したことはありますか?
A まだ一度もない・・・ランプが点滅した事があったので、いったんOFFにして再度ONにしたら元に戻った(笑)
お客様はリセットされたご様子。ランプの点滅は「お掃除サイン」なので、次回からはお掃除時期のお知らせとして確認されるようにお願いしました。

天井取り付け型の換気システムです。お客様宅では、1階・2階ともにOFFの状態でした。

Q スイッチはONにされないのですか?
A 全然、知らなかった(笑)・・・(弊社スタッフの伝達ミスです。ごめんなさい)
換気っていうと空気(ニオイ)を外に出す換気扇みたいなものですか?

お客様は「計画換気(※1)」と「換気扇」という言葉の違いに誤解があったそうです。
※1 計画換気とは、空気の入れ替えを機械的に行なうことです。詳しくは参考をご覧下さい。
(参考/2008年9月27日富山市Y邸定期点検1年目、換気システム)
(参考/2008年10月21日飛騨市T邸定期点検1年目、換気システム)
そこで、室内にある給気口を指差し確認。外の新鮮な空気を室内へ機械的に給気する圧力で、ドア下の隙間から廊下へ室内空気を押し出します。その空気を1階や2階の「換気する機械」が吸い取って外へ排気する仕組みになっています。

点検を実施。断熱材もしっかりと敷き詰められており、特に問題はありませんでした。
ここで、2階の換気システム(天井取り付け型)を確認。スイッチはONの状態でした。
1年目点検でも話題になったのですが、計画換気(法律上)する事でやっぱり廊下が肌寒くなるようですね。
(参考/2007年11月19日富山市M邸1年目点検、換気システム)
換気システムを小屋裏側から撮影。何となく・・・ムカデのような不気味な感じ。右の写真は別の部屋にダクトが抜けている様子です。
お子様が石丸や長澤のことを「変なおじさん」って何回も言っており、石丸と長澤は大変フクザツな表情、そして大きなショックを受けていたようです(笑)
そこで・・・お返し☆
石丸が点検口から室内に降りてくる時に声を低くして「怖いぞ~」と脅してみました。一瞬、「勝った!」と思いきや、やっぱりいつも通りのお子様の笑顔。無邪気で楽しいですね☆
【換気システムの掃除】
Q 1年目点検以降、換気装置のお掃除をしたことがありますか?
A ない(苦笑)
今回は、設計課の舘(一級建築士)が初の実演になりました☆
事前に用意するアイテムは、「掃除機、濡れ拭き、脚立、予備のフィルター(手持ちにあれば)」で、ドライバー等の特殊な工具はいりません。
普段のお掃除の延長と考えて頂いたほうが良いと思います。
まずは、カバーを留めているバネを手探り感覚(よっぽど高い脚立じゃないと見えません)で外します。
カバーの落下に注意して下さいね!

取り出したフィルター。ちょっと灰色になっていますが、これが空気中のホコリ等(場所によっては小さな虫も引っ掛かっています)が溜まった状態。掃除機で吸い取っている様子です。

両サイドにある2箇所の大きめのネジを手で回して白いフィルターを外します。
ちょっと回して下に引っ張ると外れます。

取り出した白いフィルターを枠から外して、掃除機でホコリ等を吸い取っています。

白いフィルターの装着時の向きに注意。途中で迷われても取り扱い説明書が貼ってあるので安心です。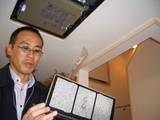

定期的なメンテナンスでは、「予備と交換」、「水洗いして日光で乾燥」、「掃除機で吸い取る」の3つの方法があります。
満足気な舘。一度、お掃除を体験すると、とっても楽しいようですね(微笑)
点検を実施。特に異常はありませんでした。画像に白い蛇腹模様のダクトが写っていますね。これが、天井取り付け型24時間換気システムの機械と外壁に取り付けてある給排気口(ベンドキャップ)へとつながっています。

小屋裏点検の際には、2階の収納(お客様宅ではクローセット内)の天井に取り付けてあるハッチを開けて、脚立と棚(棚に物がある時はずらします)を足場にして上っていきます。
点検後は、また元の状態に戻します。
ちょうど、床に何かが落ちていました。「何だろう?」と、拾って手の平に載せてしげしげと観察すると・・・虫の死骸でした。
ひと昔前のお家とは違って、最近の住宅は高気密化が進んだ反面、機械的な空気の入れ替えの必要性が出てきました。お客様宅では、第1種換気システムとなっています。
(参考/2008年10月21日飛騨市T邸1年目点検、換気システム)
(参考/2008年9月27日富山市Y邸1年目点検、換気システム)
虫の侵入経路では、床下の通気を確保する為の基礎パッキン(穴の広さは約2cm)、換気システムの給排気口(機械換気の場合は、ダクト内や換気装置)、換気扇のフード、窓の開け閉め、人(衣服に付着)の出入りの際等々、起こり得る事例は様々なようです。

空気(風)の通り道が「虫の侵入経路」にもなり得ることもあります。
防鼠材(ぼうそざい)が入って、ネズミの侵入は防いでくれますが、やっぱり小さな虫の侵入を絶つのは難しいようですね。だからといって、お家を密閉しちゃうと、窒息状態にもなりますので、虫除けアイテムを使うのも良いと思います。
(参考/2008年8月30日富山市K邸1年目点検、終わりに・・・)
お客様のお家は、第三種換気方式となっています。給気は自然で、排気は換気扇等を利用します。
排気(空気交換)が目的の換気扇等の設置場所といえば、脱衣室や階段口等ですが、点検現場でのお客様宅では、経済性を考えて電源を切っている方もおられますが・・・。
また、お部屋の壁に白い箱状の物が取り付けてあります。これが「給気は自然」の給気口で、排気の役割である換気扇から空気を外へ出す力(圧力)によって給気口から室内に外気が入ってきます。
給気口にはONとOFFの切り替えが可能となっています。冬の寒い日はONの場合、そこから冷たい空気が入ってくるので、OFFにされる方もおられるとか・・・(泣)
でも、窓を開けて換気をするほうが一番良い方法ですね。ただ、留守の時や夜は防犯上心配ですが・・・。

換気方式って何?って思う方もおられると思いますので、ここでちょっとご説明させて頂きます。
第一種換気とは、給排気ともに機械を使います。弊社でいうと天井取り付け型ですね。
第二種換気とは、給気を機械で、排気は自然にする方式ですが、一般家庭では採用されていないようです。これは、精密機械を作るクリーンルームや手術室といった、常にきれいな空気を入れなければならない場所に使われるそうですね。