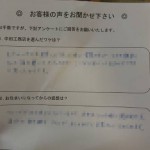モデルハウスを見学しに行った時、営業の方がとても親身になって話を聞いてくれた。ここなら安心してお任せできると思った。
[お住まいになってからの感想は?]
リビングが吹き抜けになっているので、日中はとても明るく開放的。造作の飾り棚やタイルがオシャレだと来客に褒められる。
[LDK/南側]
2階廊下にガラスブロックが埋め込まれており、LDKと繋がっています。一体感というのでしょうか。
[LDK/北側]
手の込んだ造作となっています。非常にステキな仕上がりになっています。
[造作・飾り棚]
[タイル貼り]