
【クロスの隙間】2014年9月18日(木)お家の点検10年目(高岡市T邸)
2015/03/07
クロスの一部が剥がれているのを発見。 [リビング] 今回はアフターサービスの一環で壁クロスの剥がれ箇所にコークボンドを充填して隙間を目立…
詳細を見る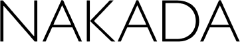

2015/03/07
クロスの一部が剥がれているのを発見。 [リビング] 今回はアフターサービスの一環で壁クロスの剥がれ箇所にコークボンドを充填して隙間を目立…
詳細を見る
2015/03/07
床下点検を実施。 特に異常はありません。床下はクモの巣が多い環境でした。床下通気口(基礎パッキン)から入ってきたものと思われます。どのお…
詳細を見る
2015/03/07
床材は木製フローリング仕様。ビニール製のクッションフロアに比べて汚れには強いのですが、水分には弱い性質があります。便器やトイレタンク周りは季…
詳細を見る
2015/03/07
「新築時の配慮がもう少しあれば防げた現象や補修等があるはず・・・」これは前回の5年目点検でのアフターメンテナンスのベテランがつぶやいた言葉で…
詳細を見る
2015/03/07
[雨水枡] 雨水枡の点検を実施。特に異常はありません。 [建物右面/北西側] [建物前面/北側] [汚水枡] 点検を実施。白い油脂等…
詳細を見る
2015/03/07
外壁同士の間に施してある弾性シーリング剤にも紫外線等による経年劣化があります。実際に指で押し当てて弾性の有無を確認することで劣化(硬化)状態…
詳細を見る
2015/03/07
Q 勝手口の扉が開閉しにくい。 [キッチン] 現状を確認。開閉時の金物を補正しました。 対処完了。支障なく上げ下げ開閉が楽になりまし…
詳細を見る
2015/03/07
折れ戸の開閉検査。横に移動する時にレール部分に引っ掛かりを発見。 [2階居室] 扉の上部にあるビスを左右からドライバーで補正。左右の動き…
詳細を見る
2015/03/07
天井クロス同士の間を見ると、コークボンドの乾いた白く透明な補修跡が太陽光で反射していました。お客様が5年目点検後にDIYでクロスの隙間にコー…
詳細を見る
2015/03/07
Q 冬の間はアルミサッシの結露が激しい。 [LDK/東側] [2階居室/南側] お客様は様々な結露対策を考えておられました。熱の伝導…
詳細を見る